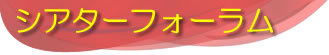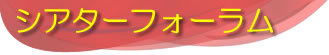そして「今回の舞台は、ミヤコ蝶々さんをモチーフにした喜劇女優の7歳からの半生記を描いたものですが、その名前は出てきません。また、登場人物は全部で10人ですが、戸田さんが演じ分ける訳ではなく、見えない人があたかも居るかのように会話が進んでいきます。
舞台の設定は昭和50年代後半、とある劇場の楽屋で、一人の女優が芝居の公演を終えて、自分の半生を、彼女の自伝を口述筆記するために来ている記者に語ります。初舞台の日からステージパパとの話、恋の話、最初の結婚の話、劇団を作って全国を廻った話、2度目の旦那の話、徐々に喜劇女優としてステータスが上がる話など。
そして50代で、これからの人生の後半、60過ぎて舞台を演っていくうえにあたって、何をどういうものをやれば良いか、どういうものに挑戦していこうか、どんな風に前向きに残された人生を生きていこうか・・・というところで、これからを予感させる形で幕を下ろします。
装置は基本的には楽屋で、場面転換ではなく、そこに置いてあっても可笑しくない小道具を使っていきます。戸田さんもメイク・衣装を変えたりせずに7歳から50代までを演じるようにするのが現在の課題で、今スタッフと頭をひねっています。」と、この作品と演出について語ってくれました。
また、科白は全て大阪弁であるため、戸田さんの要望に沿って、三谷氏が書いた脚本を俳優である生瀬勝久氏が細かく修正し、稽古場にも顔をだして方言指導をしているとのこと。単純に大阪弁にするだけではなく、そのニュアンス、感情、思いなどを含んでの言葉の選択ということで、三谷氏も「方言指導には演技力が必要だと思っていました。その点でも生瀬氏は適任、と言うか彼以外には考えられません。」と評価し、「理想は戸田さんが大阪の人間だったんだとお客様に思って貰えること。」とその成果に期待を寄せます。

「今回の目標は、ミヤコ蝶々を知っている人には楽しんでもらいたいし、名前しか知らなかったり、全く知らない世代にも、こんな人がいたことを伝えたい。出来れば外国の人にも、こんな人生を歩んだ喜劇女優がいたことを伝えたい。世界に誇れるクォリティーを持った女の一生で、“ミヤコ蝶々”の名前を外しても通る、その歩んだ凄い人生を見ていただきたい。」と力の入る三谷さん。
戸田さんとミヤコ蝶々さんとの共通点については「一見気風が良く見えて、裏側では女の情が有って、更にその奥には男らしい芯が通っている。カバーが三重に掛かっているイメージが二人に重なるので、戸田さんでこの芝居をやる必然性を感じているんです。」と語り、「一人芝居は始めてで想像がつかなかっのですが、会話や喧嘩のテンポある面白さは一人芝居でも変わらないし、――相手の科白が無いのが違いますが、――聞いて喋るので、稽古が終わると架空の出演者が居たような気がして不思議な感覚です。戸田さん以外の出演者はお客さまには見えないだけで、普通に創っていますし楽しいです。」と稽古での手応えを語ります。
「女性の話を書くのは苦手でしたが、今回は蝶々さんの恋愛の歴史にビビッと来て、ある面、恋愛遍歴のドラマになっています。一人の女性として見た時に、複雑な感情を持った人だという事が引っ掛かって、初めての女性向けドラマになっていると思います。」と三谷さん。
最後にはお二人で「初めての一人芝居で長丁場ですが、沢山の登場人物が見えたら良いなと思って稽古をしています。是非観に来てください」(戸田さん)
「楽しい一人芝居、エンターテイメントとしての一人芝居が有ることを知っていただきたい。」(三谷さん)
と締めくくり、『なにわバタフライ』の製作発表会見は終了となりました。